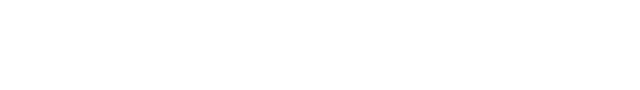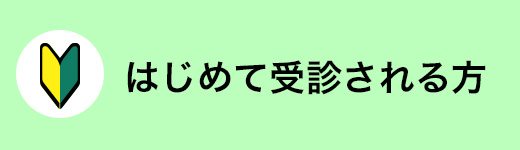中医学について
中国伝統医学
日本では一般的に「東洋医学」と言われることも多いですが、これは東洋起源の伝統医学のことを指し、中国医学(中国)、漢方医学(日本)、韓医学(朝鮮半島)など東アジアの伝統医学を全てを指しています。これらの医学はいずれも起源は中国で、中国から伝わった後、その土地の風土や気候に合わせて独自に発展を遂げていきました。
基となった中国医学は有史以前より当時の為政者(皇帝)により守られ、時代の医学者たちによって深められながら、長い年月をかけ体系が整えられた歴史ある医学です。
2,000年以上前の前漢の時代に書かれた、基礎理論から技術・実践までがまとめられた中国最古の医学書である「黄帝内経」には未病や陰陽五行説、腎の考え方など、現代の中医学でも活用されています。それまでの生薬の経験を集大成した「神農本草経」には、薬物365種類が掲載され、現代につながる基本理論が定められており、中薬学の基礎を築いたものとなっています。さらに、「傷寒雑病論(傷寒論・金匱要略)」がまとめられ、生薬を組み合わせた漢方薬の基礎が成立しました。
これら3つの書が中国医学と中薬学と漢方薬の原典とされており、現代まで研鑽され、体系が整えられ、現代の「中医学」に繋がっています。
未病先防
病気になる前に、予防することが一番とされる医学です。 古代中国では、医者のことを「工」といい、優れた医者を「上工」と呼びました。現存する中国最古の生薬の専門書である「黄帝内経」にはこのような記述があります。
・優れた医者(上工)は病気が発症する前に予防し、未病のうちに治す。
・普通の医者(中工)は病気が発症してから手を打つ。
・下手な医者(下工)は病気が進行し てしてから取り組む。
つまり中医学では天人合一という観念の元、季節、気候の変化や感情のあり方で、 身体にどのような変化が起きやすいかを察知し、発症する前の予防を第一としています。
*天人合一・・・人間は自然界の影響を受けて生活しているのであって、人体と自然界を分けて考える ことはできない。大自然を宇宙とすれば、人体は小宇宙であり、自然界で起こる様々な現象は、人体にも同じく現れるとする観念を言います。 よって、自然界の変化と疾病を関連づけて考える傾向が大きいです。