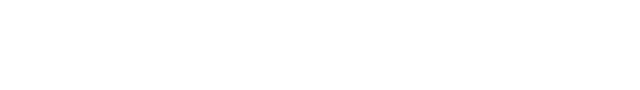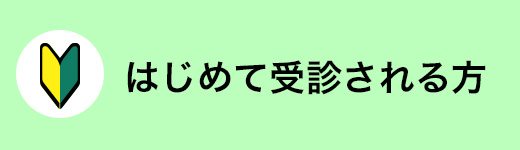糖尿病内科
当院ではこれまでも糖尿病の治療を行っておりましたが、2025/5月より糖尿病専門医の在中日を設けることになりました。より専門性の高い治療も可能となりますので、ご希望の方はご相談ください。
糖尿病の概要
糖尿病は、私たちの体にとって大切なエネルギー源であるブドウ糖をうまく利用できなくなる病気です。通常、食事から摂取されたブドウ糖は、血液によって全身に運ばれ、エネルギーとして使われます。このとき、血液中のブドウ糖の量を調節しているのが、膵臓という臓器から分泌されるインスリンというホルモンです。
インスリンは、ブドウ糖を細胞に取り込むのを助け、血液中のブドウ糖が増えすぎないようにコントロールしています。しかし、インスリンが十分に作られなくなったり、作られてもその働きが悪くなったりすると、血液中のブドウ糖がうまく細胞に取り込まれず、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が高い状態が続いてしまいます。この状態が慢性的に続くのが「糖尿病」です。
血糖値が高い状態が長く続くと、血管が傷つきやすくなり、全身の様々な臓器に悪影響を及ぼします。自覚症状がないまま進行することが多いため、気づかないうちに病気が悪化しているケースも少なくありません。しかし、適切な治療と生活習慣の改善によって、血糖値を良好にコントロールできれば、合併症を防ぎ、健康な生活を送ることが可能です。
糖尿病の症状について
糖尿病は初期にはほとんど自覚症状がないことが特徴です。そのため、健康診断で血糖値が高いことを指摘されて初めて気づく方も少なくありません。しかし、血糖値が高い状態が続くと、以下のような症状が現れることがあります。
-
のどが渇く:血糖値が高いと、体は余分なブドウ糖を尿として排出しようとします。そのため、脱水状態になりやすく、のどが渇きやすくなります。
-
尿の回数が増える、尿の量が増える:ブドウ糖が尿と一緒に排出されるため、トイレに行く回数が増えたり、一度に出る尿の量が増えたりします。
-
体重が減る:体がブドウ糖をエネルギーとして利用できなくなるため、代わりに脂肪や筋肉を分解してエネルギーを得ようとします。その結果、食事をしているのに体重が減ることがあります。
-
疲れやすい、だるい:エネルギーがうまく利用できないため、全身に倦怠感(体がだるい、疲れがとれない感じ)を感じやすくなります。
-
目がかすむ:血糖値が高いと、目のレンズである水晶体がむくみ、一時的に視力に影響が出ることがあります。
-
手足がしびれる、感覚が鈍くなる:高血糖が続くと、末梢神経(手足の感覚などを伝える神経)が傷つき、しびれや痛み、感覚の鈍さなどを感じることがあります。
-
傷が治りにくい、化膿しやすい:高血糖の状態では、免疫力(体を細菌などから守る力)が低下し、感染症にかかりやすくなったり、一度できた傷が治りにくくなったりします。
-
足がつる(こむら返り):脱水やミネラルバランスの乱れにより、足がつりやすくなることがあります。
これらの症状は、糖尿病がかなり進行してから現れることが多いです。もし、心当たりのある症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、検査を受けることをお勧めします。
糖尿病の原因について
糖尿病の原因は、いくつかの要因が複雑に絡み合って起こると考えられています。主な原因は以下の通りです。
-
インスリンの作用不足:
-
インスリンの分泌不足:膵臓のインスリンを作る細胞(β細胞:ベータさいぼう)が壊れてしまい、インスリンが十分に作られなくなることです。
-
インスリン抵抗性:インスリンは十分に分泌されているのに、その働きが悪く、細胞がブドウ糖を取り込みにくくなっている状態です。
-
-
遺伝的要因: 家族や親戚に糖尿病の人がいる場合、糖尿病になりやすい体質を受け継いでいる可能性があります。しかし、遺伝だけで必ず糖尿病になるわけではありません。
-
生活習慣要因:
-
食べすぎ、飲みすぎ:特に糖質(ご飯、パン、麺類、甘いものなど)や脂質の過剰摂取は、血糖値の上昇を招き、インスリンを分泌する膵臓に負担をかけます。
-
運動不足:運動はブドウ糖を消費し、インスリンの働きを良くする効果があります。運動不足はインスリン抵抗性を高める原因になります。
-
肥満:特に内臓脂肪の蓄積(お腹周りの脂肪)は、インスリン抵抗性を引き起こす大きな原因となります。
-
ストレス:精神的なストレスも血糖値に影響を与えることがあります。
-
喫煙:喫煙はインスリン抵抗性を高め、糖尿病の発症リスクを高めることが知られています。
-
-
その他: 特定の病気(膵臓の病気、肝臓の病気など)や、一部の薬剤(ステロイドなど)の使用が原因で糖尿病を発症することもあります。
これらの要因が組み合わさることで、糖尿病の発症リスクが高まります。特に、生活習慣の乱れは、糖尿病を誘発する大きな要因となります。
糖尿病の種類について
糖尿病は、原因によっていくつかの種類に分けられます。
1型糖尿病
自己免疫疾患(自分の免疫が自分の体を攻撃してしまう病気)などにより、膵臓のインスリンを作る細胞(β細胞)がほとんど破壊されてしまい、インスリンが全く、またはほとんど分泌されなくなるタイプの糖尿病です。子どもや若い人に発症することが多いですが、大人になってから発症することもあります。このタイプの糖尿病では、インスリン注射が必須の治療となります。
2型糖尿病
日本人の糖尿病患者さんの約9割がこのタイプです。遺伝的な要因に加え、過食、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が原因となって、インスリンの分泌が不足したり、インスリンの効きが悪くなる(インスリン抵抗性)ことで発症します。中高年以降に多く見られますが、最近では若年層でも増えています。
その他の特定の原因による糖尿病
-
-
遺伝子の異常:遺伝子の異常によって、生まれつきインスリンの分泌が少なかったり、インスリンの働きが悪かったりする糖尿病です。
-
膵臓の病気:膵臓の手術や、膵炎などの病気によって、インスリンを作る細胞がダメージを受けて発症する糖尿病です。
-
薬が原因の糖尿病:ステロイドなどの薬剤の副作用として発症する糖尿病です。
-
ホルモンの病気:特定のホルモンが過剰に分泌される病気(クッシング症候群など)が原因で発症することもあります。
-
妊娠糖尿病
妊娠中に初めて発見された、または発症した糖尿病のことです。妊娠中は胎盤からインスリンの働きを妨げるホルモンが分泌されるため、血糖値が上がりやすくなります。通常、出産後には血糖値は元に戻ることが多いですが、将来的に2型糖尿病を発症するリスクが高くなると言われています。
糖尿病の治療法
糖尿病の治療の目標は、血糖値を良好にコントロールし、合併症(腎臓病、網膜症、神経障害など)を防ぎ、健康な日常生活を送ることです。治療は、主に以下の方法を組み合わせて行われます。
食事療法
糖尿病治療の基本中の基本です。単に食べる量を減らすのではなく、何を、いつ、どのくらい食べるかが重要です。
-
-
バランスの取れた食事:主食(糖質)、主菜(たんぱく質)、副菜(ビタミン、ミネラル、食物繊維)をバランス良く摂ることが大切です。
-
適切なエネルギー量:年齢、性別、活動量に合わせて、適切なエネルギー量を摂取します。
-
規則正しい食事時間:一日三食を規則正しく摂り、間食や夜遅い食事は避けることが望ましいです。
-
食物繊維を多く摂る:野菜、きのこ、海藻など、食物繊維が豊富な食品は、血糖値の急激な上昇を抑える効果があります。
-
運動療法
食事療法と並んで重要な治療法です。
-
-
ブドウ糖の消費:運動によって筋肉がブドウ糖をエネルギーとして消費するため、血糖値を下げる効果があります。
-
インスリンの働きを良くする:運動はインスリンの効き目を良くする(インスリン抵抗性を改善する)効果があります。
-
体重管理:運動は肥満の解消にもつながり、糖尿病の改善に役立ちます。
-
有酸素運動:ウォーキング、ジョギング、水泳など、軽く汗ばむ程度の運動を毎日30分以上行うのが理想的です。
-
薬物療法
食事療法や運動療法だけでは血糖値が十分に下がらない場合に、薬による治療が行われます。
-
-
経口血糖降下薬: 飲み薬のことで、インスリンの分泌を促す薬、インスリンの効き目を良くする薬、糖の吸収を抑える薬、糖の排出を促す薬など、様々な種類があります。患者さんの病態に合わせて最適な薬が選択されます。
-
インスリン療法: インスリンがほとんど分泌されない1型糖尿病の方や、2型糖尿病で飲み薬だけでは血糖コントロールが難しい場合に、インスリンを注射で補う治療法です。近年では、ペン型の注入器が普及しており、自宅で簡単に注射することができます。
-
GLP-1受容体作動薬やGIP/GLP-1受容体作動薬: 消化管から分泌されるホルモンと同じ働きをする注射薬で、血糖値が高いときにだけインスリンの分泌を促したり、胃の内容物の排出を遅らせて食後の血糖値上昇を抑えたりする効果があります。
-
継続的な自己管理と医療機関との連携
糖尿病治療は、日々の生活習慣が大きく関わってきます。定期的に医療機関を受診し、血糖値のチェックや合併症の検査を行うとともに、食事や運動、服薬に関する指導を受けることが重要です。わからないことや不安なことがあれば、医師や看護師に積極的に相談し、一緒に治療を進めていきましょう。
当院では、患者様一人ひとりの状態に合わせた最適な治療プランを提案し、糖尿病の管理をサポートいたします。気になる症状や、血糖値についてのご相談がありましたら、お気軽にご来院ください。