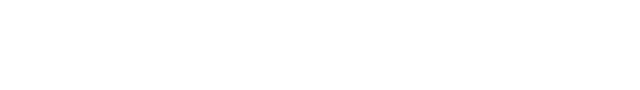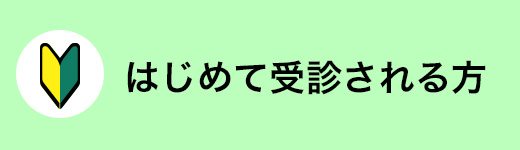生活習慣病について
食習慣、運動習慣、休養のとり方、嗜好(飲酒や喫煙)などの「生活習慣」も、糖尿病、高血圧、さらにはがん、脳卒中、心臓病など多くの疾病の発症や進行に深く関わっていることが明らかになっています。
生活習慣病
生活習慣病に該当する主な病気として
- 2型糖尿病
- 肥満症(メタボリックシンドローム)
- 脂質異常症(高脂血症)
- 高血圧症
- 腎臓病
- 心筋梗塞
- 肺がん
- 脂肪肝
- 肝硬変
などが挙げられます。
その他、生活習慣以外の要素はあるものの他の要因も影響する疾患として動脈硬化、骨粗鬆症、サルコペニア、フレイル、睡眠障害、睡眠時無呼吸症候群など
高血圧
日本高血圧学会では収縮期血圧が140mmHg以上、拡張期血圧が90mmHg以上を高血圧としています。そのまま高血圧の状態にしておくと脳や心臓の血管が動脈硬化を起こし、脳卒中や心臓病、腎臓病などの重大な病気を発症する危険性が高まります。日本人の高血圧の約8~9割が本態性高血圧(原因をひとつに定めることのできない高血圧)で、遺伝的素因(体質)や食塩の過剰摂取、肥満など様々な要因が組み合わさって発症します。中年以降にみられ、食生活を中心とした生活習慣の改善が予防・治療に非常に大切です。
脂質異常症
血液中の「悪玉」と呼ばれるLDLコレステロールや中性脂肪が増えたり、「善玉」のHDLコレステロールが減ったりした状態のことをいいます。この状態を放置していると動脈硬化が起こり、脳梗塞や心筋梗塞といった動脈硬化性疾患をまねくリスクが高まります。
脂質異常症の発症には、過食、運動不足、肥満、喫煙、過度な飲酒、ストレスなどが関係しているといわれています。「内臓脂肪型肥満」ではLDLコレステロールや中性脂肪が多くなり、HDLコレステロールが少なくなりやすい傾向があります。また、遺伝性の「家族性高コレステロール血症」と呼ばれているものもあります。一般人口の300人にひとり程度認められるとされ、比較的若年での冠動脈疾患発症のリスクがきわめて高いため、早期診断と適切な治療を受ける必要があります。
糖尿病
糖尿病は血糖値を下げる働きのあるインスリンの作用が十分でないために血液中の血糖値が慢性的に高い値を持続する病気です。インスリンを作る細胞が壊されることによる1型糖尿病と生活習慣と遺伝(体質)が関わる2型糖尿病などに分かれます。日本人においては、2型糖尿病が9割以上を占め、生活習慣病のひとつです。2型糖尿病におけるインスリンの作用不足は、体質によるものに加え、過食、運動不足、肥満、ストレスといった生活習慣が関連しています。日本人は欧米人に比べてインスリン分泌力が弱く、食の欧米化もあり患者数は増加し続けています。
血糖値が高い状態が続くと血管が障害され、動脈硬化が進行して身体の様々な臓器に影響を与えます。とくに神経や血管が集中している臓器が影響を受けやすく、三大合併症と呼ばれる糖尿病網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病神経障害を引き起こします。
また、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、末梢動脈疾患なども動脈硬化によって起こる病気であり、合併症とされます。
2型糖尿病は初期症状がほとんどなく、他の生活習慣病との関連性が深い病気です。
糖尿病の進行や重大な合併症を防ぐためにも、健康診断などで糖尿病を指摘された場合は、放置せずにきちんと受診することが重要です。
当院の治療方針
生活習慣病の改善は、まず、日常生活の改善から始まることがほとんどです。今までできなかった健康的な生活を継続していくことは、簡単なことではありませんが、日々の経過を患者さんと一緒に二人三脚で歩んでいくことを心がけます。また睡眠時無呼吸症候群の検査やCPAPのフォローも行なっております。
また、重篤な糖尿病など、高度な医療機関での治療が必要な場合には、適切な医療機関をご紹介し、紹介病院と十分な連携を取りながら、治療をすすめていきます。