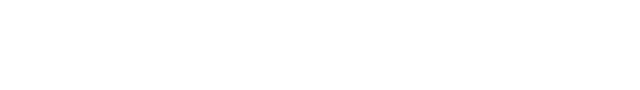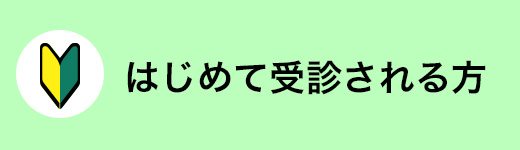夏の不調と中医学
天気がなかなか優れませんが、天候や季節などによる体調不良を中医学的にみると、夏の不調は「暑邪」と呼ばれる人体に悪影響を与えるほどの暑さなどによって引き起こされます。
そして
この暑邪に湿気の邪気である「湿邪」が絡むことで、様々な夏バテの症状を引き起こすことがあります。特に日本は湿度が高いのでこの「湿邪」も入りやすくなります。暑さにより身体の水分が失われて血液が凝縮したり、精神が乱れると五臓のうちの「心(しん)」の働きが乱れ、血行不良や不眠、精神不安、イライラを引き起こしたりもします。
そして
暑い屋外から急に冷房の効いた室内に入ると、身体は急激な冷えにさらされます。
この冷えは中医学では「寒邪」と呼ばれ、体の「陽気(体を温めるエネルギー)」を損ない、気の流れを滞らせます。
特に冷気は足元やお腹、背中、肩にたまりやすく、下記のような不調を起こすことがあります。
- お腹の冷え、下痢、腹痛
- 肩こり、頭痛
- 月経痛や生理不順
- 手足の冷え、だるさ
- 自律神経の乱れ(不眠、動悸、めまい など)
中医学では、外邪(風・寒・暑・湿など)から体を守る力を「衛気」と呼びます。衛気は皮膚や筋肉の表層を巡っており、体温を調節したり、邪気の侵入を防ぐ働きをしています。
しかし以下のような状態になると、「衛気」が弱まり、気温差の影響を強く受けてしまいます。
- 過労や睡眠不足で「気虚」の状態
- 冷たいもの・甘いものの摂りすぎで「脾」が弱っている
- 汗をかきすぎて「気」や「津液」が消耗している
夏は体力(気)が消耗しやすく、「衛気」も弱りやすいため、冷房や気温差による「寒邪」が侵入しやすくなってしまいます。
まずは睡眠をよくとって規則正しい生活をすること。定期的な運動を取り入れ、こまめに少しずつ水分を摂ることや、甘い物・脂っこい食べ物は控えるようにすると良いと思います。
なかなか体調不良が治らない方は当院にご相談くださいね。